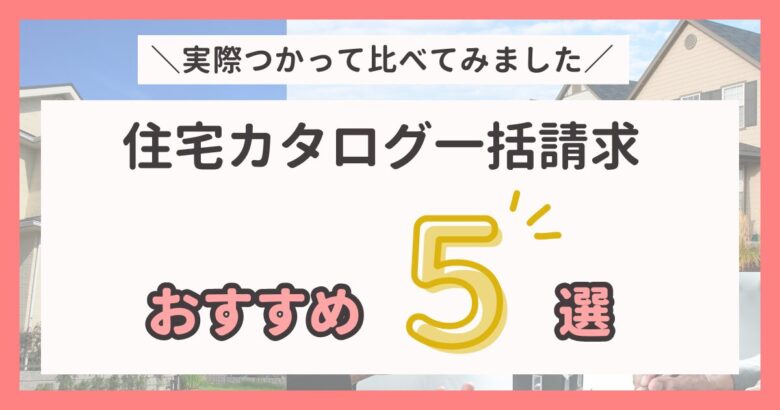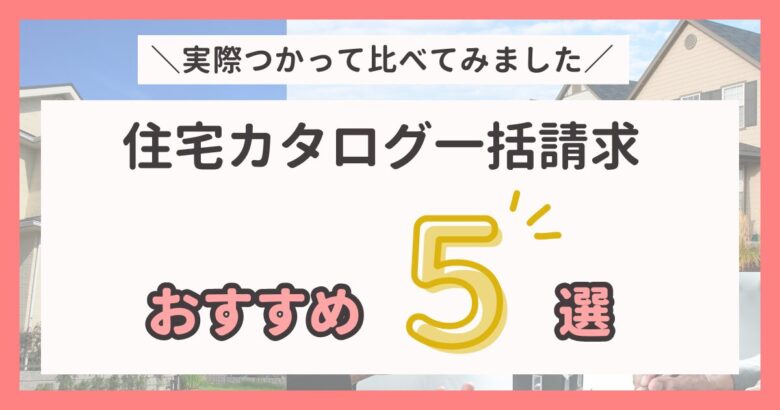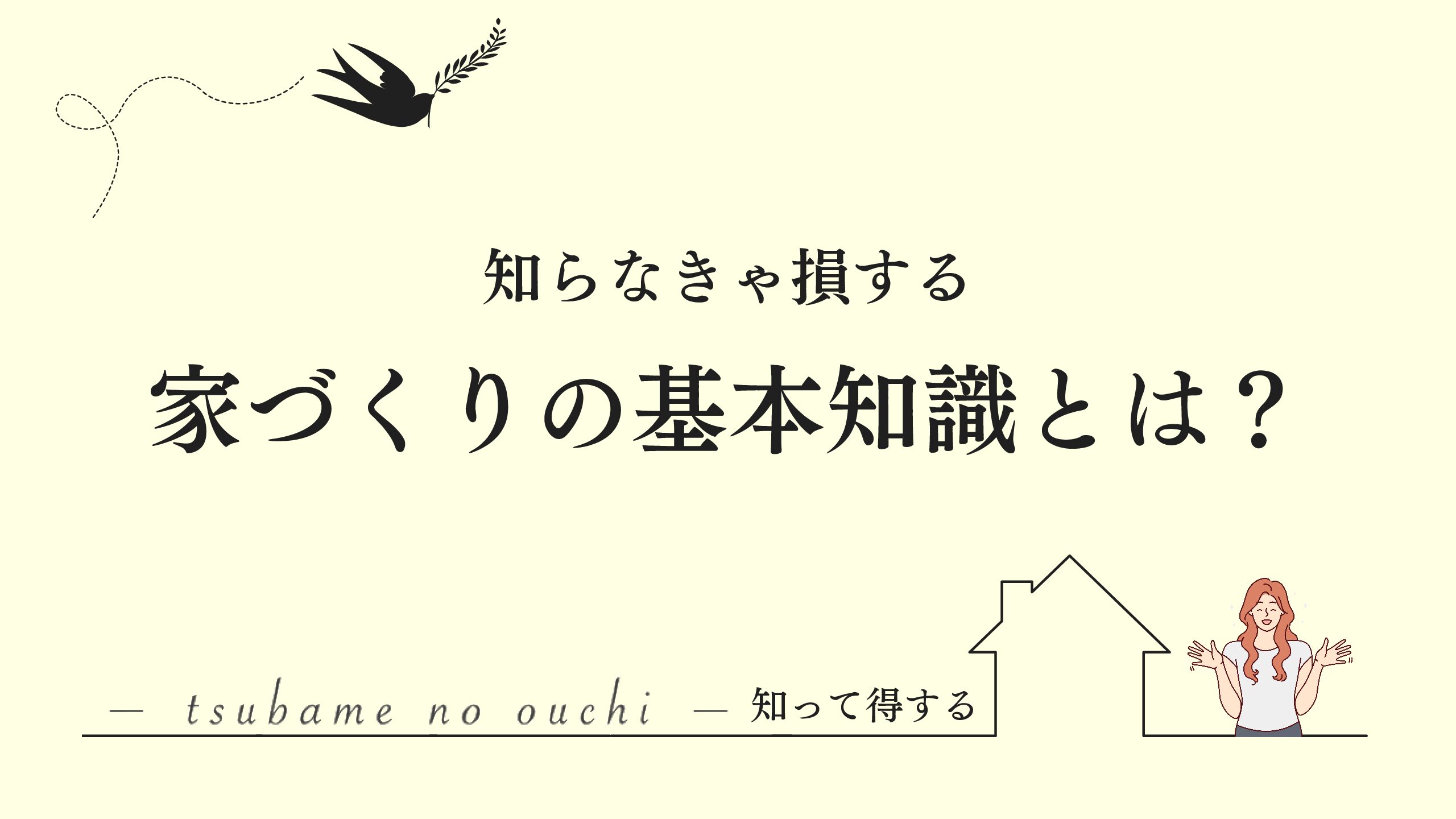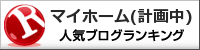注文住宅を考えたらまず見てほしい。工務店・メーカー選び時に後悔しない家づくりのための情報を詳しくご紹介します。
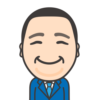 つばめ
つばめおはようございます。こんにちは。こんばんは。つばめです。
このブログでは、私が工務店営業担当時代には立場上言えなかった情報や本音をお伝えしています。
一生に一度の買い物、あなたには後悔してほしくない!
読んで知って、賢くあなたの夢のマイホームを実現させましょう。
元工務店営業担当の私の主張はただひとつ!
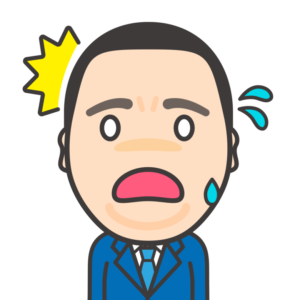
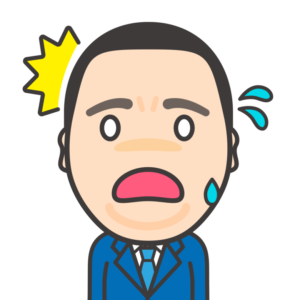
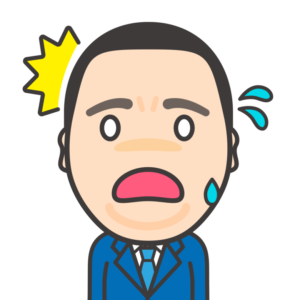
家を建てるときに大事なのは比較検討すること
そのために、複数の会社から見積もりをとりましょう。
住宅展示場にふらっと行くのはNGです。»NGな理由
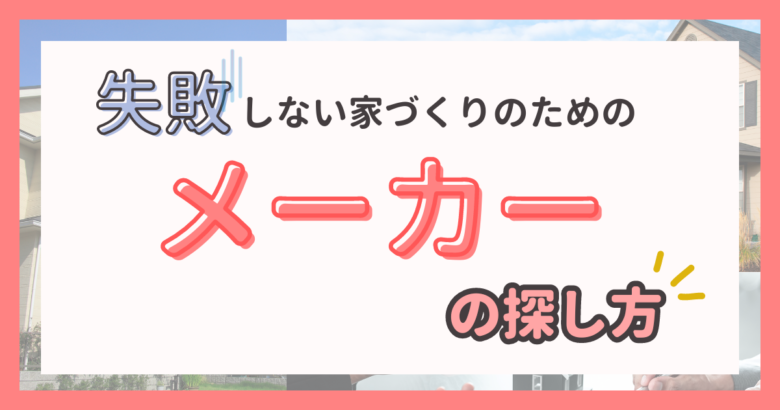
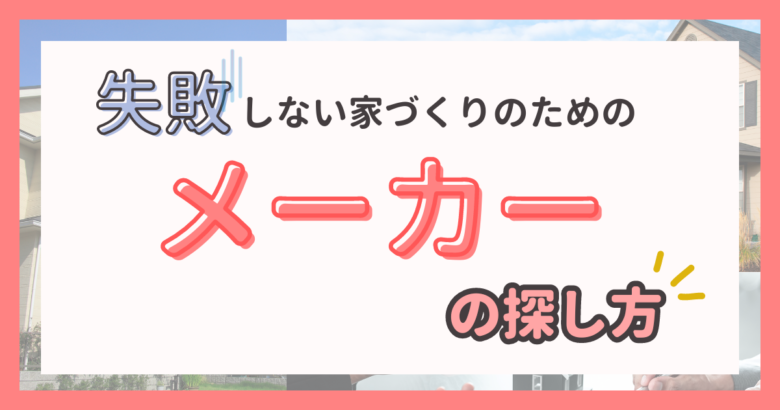
忙しくて簡単に情報収集したい方は
情報収集には住宅カタログ一括請求がベストです。情報収集が簡単で、家でゆっくりと検討もできます。
まだいろいろなカタログを見比べていない方は絶対にするべきです。
\無料 簡単3分 ネットで完結/
» 公式 LIFULL HOME’Sで注文住宅の一括資料請求



今あなたの一歩できっと違う結果に!
やって損はないから絶対やって!
契約はリスクがあるけど情報収集はノーリスクだよ!
時間をかけても自分に合った
ぴったりなメーカーが知りたい方は
【PR】
スーモカウンターなら、カタログだけではわからない情報まで!!あなたの予算・要望にあった理想の建築会社を紹介してくれます。
\利用者満足度96.8%* 理想の建築会社が見つかる/
*スーモカウンター ご利用者アンケート/2023年5月 自社調べ



全て無料で家づくり講座も充実!家づくり初心者大歓迎!
土地探し、間取り、資金計画など全て相談したい方におすすめです。
予約を取ることでスムーズです。
住宅ローンで破綻しないための方法


住宅を購入する際、多くの方が住宅ローンを利用しますが、ローン返済に苦しむケースも少なくありません。せっかくのマイホーム購入が、家計の重荷になってしまっては元も子もありません。



住宅ローンで破綻しないために知っておきたいポイントをお伝えします。
年収UP、退職金 (将来期待の計画は危険)
将来的に年収が上がる、退職金が期待できるという計画に頼るのは非常にリスクがあります。将来の収入が確実でない限り、現実的な収入に基づいてローンの計画を立てることが重要です。
ライフステージの変化 (中立なプランナーに相談)
家族構成や生活スタイルは時間とともに変わっていきます。これを見越して、住宅ローンを組む前に中立な立場のファイナンシャルプランナーに相談し、将来的な変化を考慮に入れた計画を立てましょう。
返済比率の管理 (年収の25%以下が目安)
住宅ローンの返済比率は、年収の25%以下に抑えることが目安です。年収の25%以上の比率になると、生活費や他の支出に影響が出て、家計が圧迫される可能性があります。
ボーナス払い (ないものとして計算)
住宅ローンの返済にボーナス払いを組み込むのは危険です。ボーナスが減額されたり、出なかったりする可能性もありますので、ボーナスはあてにせず、月々の返済額のみで計画を立てましょう。
家賃と同じなら大丈夫 (税金やメンテ費用も考慮)
現在の家賃と同じ金額のローン返済なら問題ないと思われがちですが、住宅を所有すると固定資産税やメンテナンス費用がかかります。これらも含めた支出を考慮して、無理のない返済計画を立てましょう。
固定金利の検討 (金利上昇リスクを回避)
金利が低い変動金利は魅力的ですが、将来的な金利上昇リスクがあります。固定金利ならば、一定期間の返済額が確定しているため、安心して返済を続けられます。
余裕資金の確保 (急な出費に備える)
急な出費や収入減少に備えて、一定の余裕資金を確保しておくことが大切です。予想外の事態が発生しても、余裕資金があれば対応でき、ローン返済が滞るリスクを軽減できます。
住宅ローンは長期間にわたる大きな支出ですので、しっかりとした計画を立てることが重要です。ここで紹介したポイントを参考に、自分に合った無理のないローン計画を立ててください。



将来の安心と快適な生活を手に入れるために、慎重に考え、準備を進めていきましょう。
住宅・土地購入時、知っていた方が良い単語


住宅や土地の購入は、大きな決断を伴う人生の一大イベントです。その際には、いくつかの重要な専門用語や概念を理解しておくことが、トラブルを避け、スムーズに進めるための鍵となります。



これから家を買おうとしている方に向けて、知っておくと役立つ7つの基本的な単語を紹介します。
所有権/借地権/抵当権(超キホン)
住宅や土地に関する最も基本的な権利の種類です。所有権は、土地や建物を完全に所有する権利。借地権は、土地を借りて使用する権利です。そして、抵当権は、住宅ローンを組む際に銀行などが担保として設定する権利です。これらはすべて、購入前にしっかり理解しておくべき重要なポイントです。
手付流し手付倍返し(解約の方法)
不動産取引における解約の方法の一つです。買主が契約を解除したい場合、手付金を放棄(手付流し)することで解約が可能です。また、売主が契約を解除したい場合、手付金の倍額を買主に返す(手付倍返し)必要があります。この方法を理解しておくことで、契約後のトラブルを避けられます。
インスペクション(建物現状の外部検査)
これは、建物の現状を第三者の専門家が検査することを指します。住宅の状態を客観的に把握するために、購入前にインスペクションを行うことをお勧めします。これにより、見逃しがちな修繕の必要性や潜在的な問題を事前に把握できます。
再建築不可(建替が出来ない)
再建築不可の土地は、その場所に新たに建物を建てられない土地です。古い建物を取り壊して新築を建てたいと考えている場合、この条件を持つ土地は避けるべきです。
瑕疵担保責任・契約不適合責任(売主の責任事項)
これらは、売主が負う責任事項です。瑕疵担保責任とは、隠れた欠陥に対する売主の責任で、契約不適合責任とは、契約内容に合わない点があった場合の売主の責任です。購入後に発見される問題に対して、どのような補償があるかを理解しておくことが重要です。
公簿売買・実測売買(土地の取引方法)
これは、土地の取引方法に関する用語です。公簿売買は、登記簿に記載された面積を基準に売買する方法。一方、実測売買は、実際に測量した面積を基に取引を行います。正確な取引を行うためには、どちらの方法が用いられているかを確認する必要があります。
フラット35(長期固定金利の住宅ローン)
フラット35は、長期固定金利の住宅ローンで、住宅金融支援機構が提供しています。金利が変動しないため、返済額が一定で、将来の金利上昇リスクを避けたい方にとって安心な選択肢となります。
住宅や土地の購入は、専門的な知識が求められる大きな取引です。ここで紹介した7つの単語を理解しておくことで、購入プロセスを安心して進められます。



家づくりや不動産購入の際に、これらの知識が役立つことを願っています。
不動産売買契約の重要ポイント


不動産を購入する際、契約書に目を通すことは非常に重要です。しかし、その内容は専門的で難解なことが多く、見落としてはいけないポイントがいくつも存在します。



大切な資産を守るためにも、契約時に必ず確認すべきポイントをしっかりと理解しておきましょう。
ローン条項(期間が短い場合は注意、二週間〜1ヶ月)
ローンの承認が得られなかった場合に契約を白紙撤回できる条項ですが、期間が短すぎるとリスクが高くなります。通常は二週間から1ヶ月程度が一般的ですが、それより短い期間を設定されている場合は注意が必要です。ローン審査に十分な時間を確保できるようにしましょう。
公簿売買(土地面積の違いや近隣トラブルの可能性)
公簿売買とは、土地の登記簿上の面積を基に売買する方法です。しかし、実際の面積と異なる場合があり、特に土地の境界や近隣とのトラブルが起こりやすい点に注意が必要です。正確な面積を知るためには、実測売買を選択することも検討しましょう。
クーリングオフ(基本的にない、解約は手付放棄)
不動産売買には基本的にクーリングオフ制度は適用されません。そのため、契約を解約したい場合には手付金を放棄する形で進めることになります。この点を理解しておかないと、契約後に解約を希望した際に大きな損失を被る可能性があります。
特約(罠があるとしたらここ)
契約書に記載される特約は、売主と買主の間で特別に定められた条件です。この部分に予期せぬ罠が潜んでいることもありますので、内容をしっかり確認し、不明な点があれば納得いくまで質問することが大切です。
手付金(契約解除時の取り扱いを確認)
手付金は契約時に支払われ、契約解除時の取り扱いが定められています。特に、買主が契約を解除する場合には手付金が戻ってこないことが多いため、その取り扱いについて事前にしっかり確認しておくことが必要です。
境界確認(隣接地との境界を明確に)
不動産の取引において、隣接地との境界が不明確だと後々トラブルになる可能性があります。契約前に境界をしっかりと確認し、隣接する土地の所有者と合意が取れているかどうかも確認することが重要です。
引渡し条件(引渡し時の物件状態をチェック)
物件の引渡し時に、どのような状態で引き渡されるかを明確にしておくことが必要です。引渡し時の物件の状態が契約内容に合致しているかどうかを確認し、もし問題があれば速やかに対応できるように準備しておきましょう。
不動産売買契約は、人生の中でも大きな決断の一つです。契約時に重要なポイントをしっかり押さえておくことで、後々のトラブルを避けられます。



ここで紹介した7つのポイントを参考に、安心して不動産取引を進めてください。
住宅を持つ初めの一歩


住宅を持つことは、多くの人にとって夢であり、人生の大きな目標です。しかし、初めての住宅購入や建築には、計画的な準備と情報収集が不可欠です。



住宅を持つために最初に踏み出すべき7つのステップを紹介します。
話し合い (家族で建築理由を共有)
まず、家族で住宅を持つ理由や目的を共有することが大切です。家を建てる理由がはっきりしていると、家族全員が同じ方向を向いて進められます。将来のライフスタイルや希望を話し合いながら、共通の目標を確認しましょう。
知識武装 (web、動画、本等で学習)
住宅購入や建築に関する知識をしっかりと身につけることが重要です。インターネットや動画、本などを活用して、基本的な情報や最新のトレンドを学びましょう。知識があれば、後々の判断も的確に行えるようになります。
ライフプラン作成し予算決める (中立なFPに相談)
ライフプランを作成し、その上で予算を決めることが重要です。中立なファイナンシャルプランナー(FP)に相談することで、現実的な資金計画を立てられます。これにより、無理のない予算設定が可能です。
何に住むか勉強して決める (各住宅タイプの特徴把握)
住宅には様々なタイプがあります。マンション、一戸建て、建売住宅など、それぞれに特徴があります。自分たちのライフスタイルや将来の計画に合った住宅タイプを選ぶために、各タイプの特徴を理解し、どれが自分たちに最適かを考えましょう。
立地調査 (通勤、学校、買い物の利便性)
住む場所の選定は非常に重要です。通勤や学校、買い物の利便性を考慮して、希望するエリアの調査を行いましょう。立地が生活に与える影響は大きいため、十分な時間をかけて選定することをお勧めします。
資金計画 (頭金、ローン、諸経費を検討)
頭金やローン、諸経費などの資金計画を立てることが必要です。無理のないローンの組み方や、予想される諸経費をしっかりと計算して、計画を立てましょう。これにより、後から予想外の出費に悩まされることを防げます。
専門家選び (信頼できる不動産業者、建築士探し)
信頼できる不動産業者や建築士を見つけることが、住宅購入や建築の成功に繋がります。専門家は多くの経験と知識を持っていますので、信頼できるパートナーを選び、一緒にプロジェクトを進めることが大切です。
住宅を持つことは、人生の大きなステップです。ここで紹介した7つのステップを踏むことで、安心して住宅購入や建築のプロセスを進められます。



家族と共に話し合い、十分な準備をして、理想の住まいを手に入れましょう。
住宅購入・建築の選択肢


住宅購入や建築を考える際、さまざまな選択肢があり、それぞれに特徴やメリットがあります。自分のライフスタイルや予算に合った最適な選択をするためには、各選択肢の特徴を理解することが重要です。



ここでは、住宅購入・建築における主要な選択肢を7つ紹介します。
注文住宅 ハウスメーカー・工務店
完全オーダーメイドで、自分たちの希望を反映した理想の家を建てられます。ハウスメーカーは規格化されたプランが多く、安定した品質が期待できますが、工務店を選ぶと、より個性的な設計や細かい対応が可能です。予算に応じて、自由度の高さを楽しめます。
新築マンション
新築ならではの最新設備や綺麗な環境が魅力です。セキュリティや共用施設が充実していることが多く、管理がしっかりしているため、安心して暮らせます。駅近など利便性の高い立地にあることが多いのもポイントです。
セミオーダーの売建住宅
既存の設計プランに一定のカスタマイズを加えられるセミオーダー形式です。注文住宅ほど自由度は高くありませんが、コストを抑えつつ、個別の要望をある程度反映させられます。
建売住宅
既に建てられた家を購入する形の住宅です。完成済みの物件を見てから購入を決められるため、実際の住み心地を確認しやすいです。注文住宅に比べて価格が抑えられており、手続きも比較的スムーズです。
中古マンション・戸建て
予算を抑えつつ、希望するエリアに住む選択肢です。新築と比べて手頃な価格で購入できることが多く、選択肢が広がります。ただし、築年数やメンテナンス状態によっては追加のリフォームが必要になることもあります。
中古マンション・戸建て購入後リノベーション
既存の中古物件を購入してから、自分の好みに合わせてリノベーションを行う方法です。建物の骨組みを活かしつつ、内装や設備を新たに設計できるため、新築では手に入れられない独自の空間を作り出すことが可能です。
中古リノベーション済マンション・戸建て
既にリノベーションが完了した物件を購入する選択肢です。手間をかけずに、最新の内装や設備が整った住宅に住めるため、リノベーションの計画や工事の手間を避けたい方におすすめです。
住宅購入や建築には多くの選択肢があり、それぞれに異なるメリットがあります。自分たちのライフスタイルや予算、将来の計画に合った選択をするために、ここで紹介したポイントを参考にしてみてください。
恐ろしい欠陥住宅
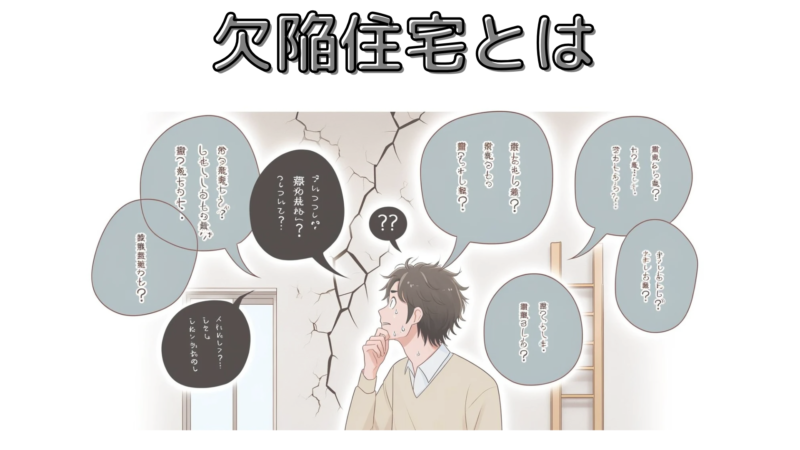
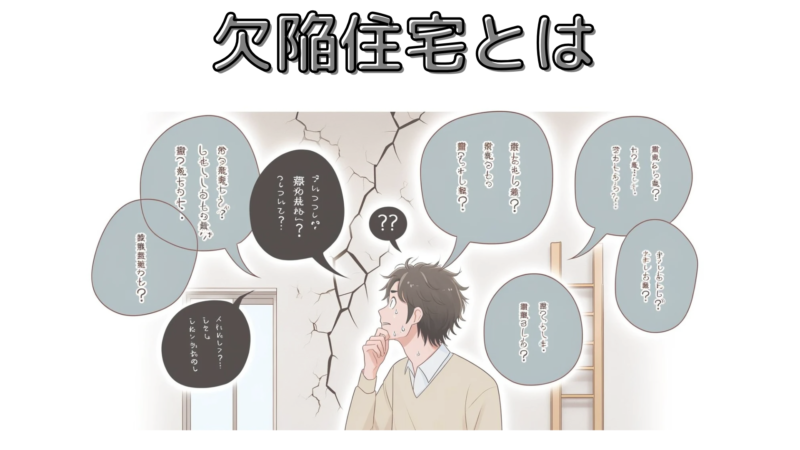
住宅は、家族が安心して暮らせる場所であるべきですが、もしそこに欠陥が潜んでいたらどうでしょうか。見た目には分からなくても、隠れた欠陥が原因で大きなトラブルや危険に繋がることがあります。



ここでは、特に恐ろしい欠陥住宅の例を7つ紹介します。
外壁のシーリング隙間だらけ(雨水浸入して雨漏り原因)
外壁のシーリングに隙間があると、隙間から雨水が浸入し、雨漏りの原因となります。見た目には気づきにくいですが、雨漏りが発生すると構造躯体が徐々に傷んでしまい、大規模な修繕が必要になることもあります。
雨漏り(構造躯体が傷むのが怖い)
雨漏りは住宅の大敵です。構造躯体が雨水にさらされ続けると、木材が腐食し、建物の強度が低下します。最悪の場合、建物全体の寿命が大幅に短くなる可能性があるため、早期に発見して対策を講じることが重要です。
排水管の詰まり(配管勾配が問題。フラットや逆勾配はヤバい)
排水管の勾配が適切でないと、水がスムーズに流れず、詰まりの原因になります。特に、フラットや逆勾配になっている場合は要注意です。排水の問題は衛生面にも影響するため、早めの点検と修理が必要です。
構造強度(揺れる、窓サッシ動き悪い特徴)
建物が揺れ、窓サッシの動きが悪い場合、構造強度に問題がある可能性があります。地震時などは特に危険で、建物全体の安全性が大きく損なわれるリスクがあります。専門家による診断が必要です。
断熱不良(冬は寒く夏は暑い)
断熱が不十分な住宅は、冬は寒く、夏は暑いという非常に不快な環境になります。さらに、冷暖房費がかさみ、エネルギー効率も悪化します。断熱性能を確認し、必要に応じて改善することが重要です。
電気配線の不備(火災のリスク)
電気配線の不備は、火災のリスクを高めます。配線が不適切な場所にあったり、古くなっている場合、ショートや過熱が発生しやすく、最悪の場合は火災に繋がります。安全性を確保するために、配線の状態を定期的にチェックしましょう。
地盤沈下(家全体が傾く)
地盤沈下が起こると、家全体が傾き、建物の構造が深刻なダメージを受けます。ドアや窓が正常に開閉できなくなるなど、生活にも支障をきたすことが多く、修復には高額な費用がかかる場合があります。
欠陥住宅は、見えないところに潜む危険が多く、気づかないうちに大きな問題へと発展することがあります。



安心して暮らせる住まいを選ぶことが大切です。
重要な自宅維持費用


住宅を購入した後も、長く快適に暮らし続けるためには、定期的なメンテナンスや維持費用が必要です。しかし、これらの費用を見落としてしまうと、予期しない出費に悩まされることになります。



ここでは、住宅を維持するために考慮すべき重要な費用について紹介します。
税金・保険(固定資産税・都市計画税・火災地震保険)
自宅を持つと、固定資産税や都市計画税が毎年かかります。また、火災保険や地震保険も、家を守るために欠かせない費用です。これらの税金や保険料は、住宅ローンと同様に毎年の支出としてしっかり計画に組み込んでおくことが重要です。
自治会費(未加入のリスク有)
地域によって異なりますが、自治会に加入するための費用もかかる場合があります。自治会に未加入だと、地域の情報やサポートを受けられないリスクがあるため、加入することをお勧めします。
設備の修理費交換費用(エアコン・トイレ・給湯器・お風呂・キッチン等)
エアコン、トイレ、給湯器、お風呂、キッチンなどの住宅設備は、時間が経つにつれて修理や交換が必要になります。これらの設備が故障した場合、迅速に対応できるよう、一定の資金を準備しておくことが大切です。
屋根外壁のメンテナンス(5年~15年の頻度)
屋根や外壁は、5年から15年に一度の頻度でメンテナンスが必要です。定期的にチェックし、ひび割れや劣化が見られた場合は、早めに補修を行いましょう。これにより、建物全体の寿命を延ばし、修繕費用を抑えられます。
定期清掃・管理費(庭の手入れや外構の維持)
庭の手入れや外構の維持も、住宅を快適に保つためには欠かせません。雑草の除去や植栽の剪定など、定期的な清掃と管理が必要です。これを怠ると、見た目だけでなく、家の価値にも影響を与える可能性があります。
給排水設備の点検(配管の定期的な点検・清掃)
給排水設備は、配管の詰まりや漏水を防ぐために、定期的な点検と清掃が必要です。配管の状態を定期的にチェックし、必要に応じてクリーニングや修理を行うことで、大きなトラブルを未然に防げます。
セキュリティ費用(防犯設備の更新・維持)
防犯設備の更新や維持も重要です。セキュリティカメラやセンサーライトなどの設備は、古くなると効果が薄れるため、定期的に点検し、必要に応じて最新の設備に更新しましょう。安心して暮らすための投資として、セキュリティ費用を忘れずに考慮しましょう。
住宅を長期間にわたって快適に維持するためには、これらの費用を計画的に管理することが不可欠です。日々の生活を楽しむためにも、しっかりとメンテナンスを行い、予期せぬトラブルを防ぐよう心がけましょう。



自宅を大切にし、安心して暮らせる住まいを維持するために、これらのポイントを参考にしてみてください。
容積不算入で広く作れる裏ワザ


家を建てる際、限られた敷地や建ぺい率・容積率の制限の中で、いかに広く快適な空間を確保するかは、設計の腕の見せ所です。実は、容積率に算入されない空間を巧みに活用することで、実際の居住スペースを広げる「裏ワザ」が存在します。



ここでは、容積不算入で広く作れる7つの方法を紹介します。
ロフト(子供は喜ぶ、要エアコン)
ロフトは、特に子供たちにとって魅力的な空間です。ベッドルームや遊び場として利用でき、容積率には算入されないため、実際の床面積を有効に拡大できます。ただし、夏場は暑くなるため、エアコンの設置が必要になる場合があります。
防災備蓄庫(震災以降の新ルールで使い方無検査)
震災以降、新たに導入されたルールにより、防災備蓄庫は容積率に算入されません。万が一の備えとしても非常に有用でありながら、広さを確保するための工夫としても活用できます。使い方についての検査もないため、柔軟に設置可能です。
『くら』という床下収納(1階2階の間に収納、高さ1.4m)
1階と2階の間に設置される床下収納、「くら」は、高さ1.4メートル以下の空間であり、容積率に含まれません。収納スペースとして活用できるだけでなく、家全体の収納力を向上させる有効な方法です。
小屋裏収納(使いにくいが不算入)
小屋裏収納は、天井裏に作られた収納スペースで、使いにくいことが多いですが、容積率に算入されないため、スペースを広く使いたい方にとっては魅力的です。季節ものやあまり使わない物の保管場所として活用できます。
ピロティ駐車場(駐車スペースとして利用)
ピロティ駐車場とは、建物の1階部分を駐車スペースとして利用する方法です。容積率には含まれず、駐車スペースとして確保できるため、土地の有効活用にも繋がります。加えて、駐車場の上に住居スペースを設けられます。
テラス(屋外スペースとして有効利用)
テラスは、屋外スペースとして有効に利用でき、容積率には含まれません。食事を楽しんだり、ガーデニングを楽しんだりと、居住空間を拡張する方法として人気です。開放感を演出し、自然との調和を楽しむスペースとして活用しましょう。
吹き抜け(開放感を演出)
吹き抜けは、天井を高くすることで開放感を生み出すデザイン手法です。容積率に算入されないため、リビングや玄関に取り入れることで、空間に広がりを持たせられます。光を取り込み、明るく快適な住空間を作り出します。
容積率を考慮しながらも、広く快適な住まいを実現するためには、これらの「裏ワザ」を活用することが効果的です。



限られた空間を最大限に活用し、家族みんなが快適に過ごせる住まいを目指して、これらの工夫を取り入れてみてください。
終の住処を!新築時に老後対策を考える
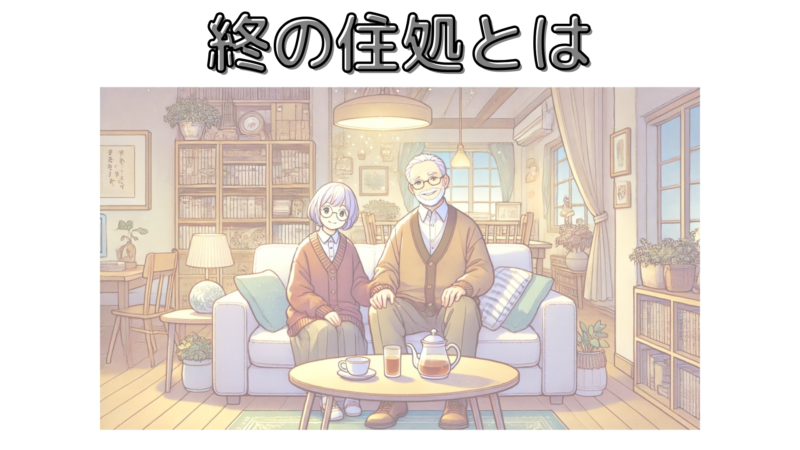
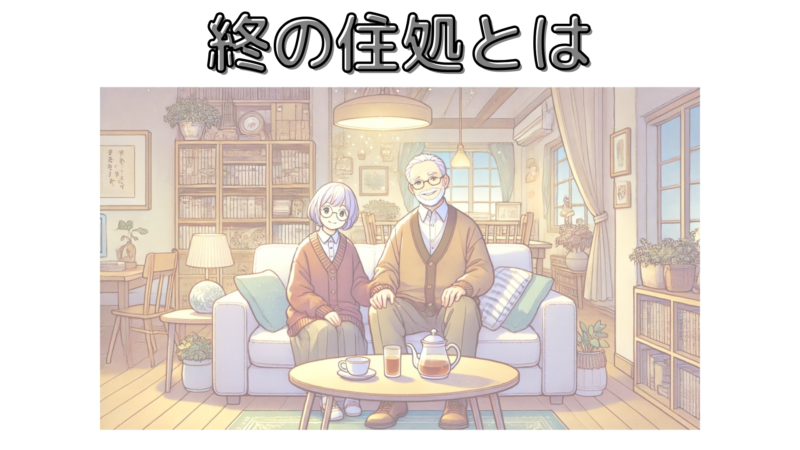
終の住処を新築する際、老後を見据えた設計を考えることは非常に重要です。年齢を重ねると、住まいの使い勝手や安全性が生活の質に直結します。これからの人生を快適に過ごすために、今からしっかりと老後対策を考えた家づくりを検討してみましょう。



ここでは、新築時に取り入れるべき7つの老後対策について紹介します。
廊下を通りやすく(なるべく減らす、曲り角をなくす)
廊下はできるだけ短くし、曲り角をなくすことで、移動がスムーズになります。車椅子や歩行補助具を使用する可能性を考えると、通りやすい廊下の設計は重要です。シンプルで広々としたレイアウトにすることで、将来の移動を楽にします。
引戸一択(車椅子での開戸は困難)
引戸は、開戸に比べて車椅子でも使いやすく、開閉時のスペースを取らないため、老後の生活に適しています。重い扉や狭いスペースでの開閉の苦労を避けるために、すべてのドアを引戸にすることをお勧めします。
洗濯物(干すスペースを1階に確保。ランドリールーム作る。外に干す)
洗濯物を干すスペースを1階に設けることで、階段を使わずに家事をこなせます。ランドリールームを作ることで、雨の日でも快適に洗濯物を干せますし、晴れた日には庭などの屋外スペースに干すことも可能です。
水廻り(まとめて動線を良くする)
キッチン、バスルーム、トイレなどの水廻りを一箇所にまとめることで、動線を短くし、家事や日常の動きを楽にします。老後の体力を考えると、無駄な移動を減らすことが大切です。
バリアフリー設計(段差をなくす)
すべての部屋に段差をなくし、バリアフリー設計にすることで、将来的な転倒リスクを大幅に減らせます。スムーズな移動が可能になり、家全体が安心して過ごせる空間となります。
トイレを広めに(介助スペース確保)
トイレは、介助が必要になった場合を考慮して、広めに設計しましょう。車椅子や介助者が一緒に入れるスペースを確保することで、安心して利用できるようになります。
階段の緩やかさ(将来的に昇降しやすく)
階段の勾配を緩やかにすることで、将来的に昇り降りが楽になります。また、階段の幅を広くし、手すりを設置することで、さらに安全性を高められます。老後を考えた場合、将来の階段の使いやすさは非常に重要です。
老後を見据えた住まいづくりは、将来の生活の質を大きく左右します。新築時にこれらのポイントを取り入れることで、年齢を重ねても快適で安全な住まいを実現できます。



長い目で見て、自分自身や家族が安心して暮らせる住まいを計画しましょう。
あった方が良い防犯対策


家を守るためには、防犯対策が欠かせません。安心して暮らすためには、侵入者を寄せ付けない工夫が必要です。



ここでは、自宅を安全に保つためにあった方が良い防犯対策を7つ紹介します。
防犯アピール(監視カメラを見える場所に設置)
監視カメラを見える場所に設置することで、侵入者に対して「この家は防犯対策がしっかりしている」というアピールができます。見えるところにカメラがあるだけで、犯罪を未然に防ぐ効果が期待できます。
IOT導入(窓やドアの閉め忘れ通知)
窓やドアの閉め忘れを通知するIOTデバイスを導入することで、外出先でも家の状況を確認できます。万が一閉め忘れた場合も、リモートで施錠ができるため、安心感が高まります。
高い塀や樹木をやめる(死角が多いと危険)
高い塀や茂った樹木は、外からの視線を遮りプライバシーを守る一方で、死角を作ってしまい、逆に犯罪者の隠れ場所となるリスクがあります。見通しの良い環境を保つことで、侵入を未然に防ぎます。
ポストや玄関周りの掃除(隙がある家に見せない)
ポストや玄関周りが散らかっていると、留守にしていると勘違いされることがあります。定期的に掃除をして、家が常に管理されていることを示すことで、隙のない家として認識されやすくなります。
ガラス進入対策(補助錠や防犯フィルム)
補助錠や防犯フィルムを窓に取り付けることで、窓ガラスからの侵入を防げます。特に、窓が割れてもすぐには破れない防犯フィルムは、侵入者を躊躇させる効果があります。
玄関の二重ロック(侵入を難しくする)
玄関ドアに二重ロックを設置することで、侵入にかかる時間を増やし、侵入者を諦めさせられます。手間はかかりますが、二重ロックは非常に効果的な防犯手段です。
センサーライト設置(人が近づくと点灯)
玄関や駐車場にセンサーライトを設置し、人が近づくと自動で点灯するようにします。これにより、不審者が近づいた際に驚かせる効果があり、犯行を抑止できます。
防犯対策は、家族の安全を守るために非常に重要です。ここで紹介した7つの対策を取り入れることで、犯罪を未然に防ぎ、安心して暮らせる住まいを実現しましょう。



日常の小さな心がけが、大きな安心につながります。
危険な住宅ローンの思考
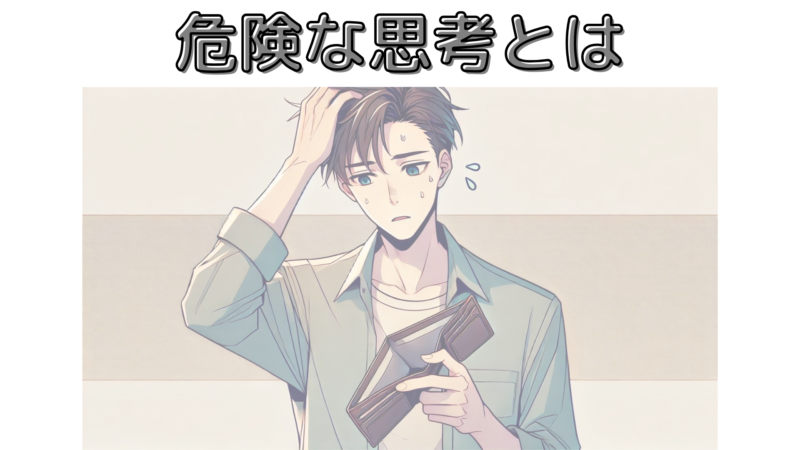
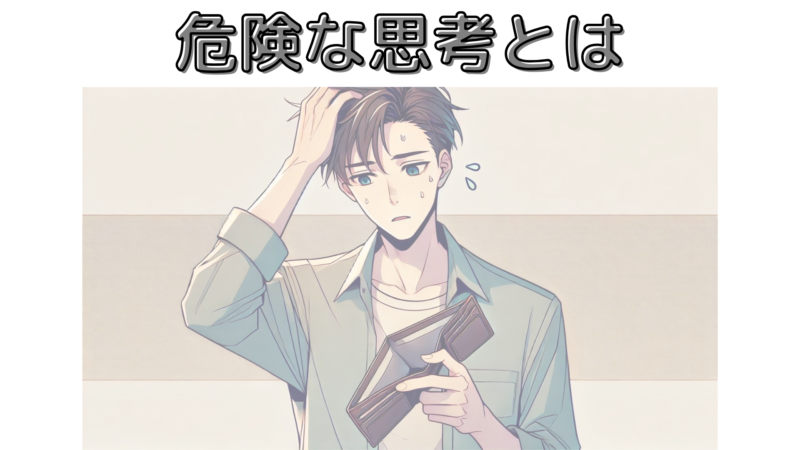
住宅ローンを組む際、多くの人が夢のマイホームを手に入れるために、将来の収入や状況を楽観的に考えがちです。しかし、その思考が危険な罠となり、後々の生活に大きな負担をもたらす可能性があります。



ここでは、特に危険な住宅ローンに関する思考パターンを7つ紹介します。
転職して年収アップすればいい
住宅ローンを組む際に、「転職して年収を上げれば、返済は楽になる」と考えるのは非常に危険です。転職が必ずしも成功するとは限らず、逆に収入が不安定になるリスクもあります。現状の収入を基に無理のないローンを組むことが重要です。
昇給・昇進があるから大丈夫
将来の昇給や昇進を前提にしたローン計画も危険です。企業の業績や経済状況によっては、昇給や昇進が思うように進まないこともあり、計画が狂うリスクがあります。確実な収入に基づいて返済計画を立てるべきです。
ボーナス返済を前提に計画する
ボーナス払いを前提とした返済計画は、ボーナスが減額されたり、出なくなった場合に大きなリスクとなります。ボーナスは不確定要素が多いため、安定した月々の収入で返済できる計画を立てることが大切です。
子供が生まれて、仕事をずっと続ける
子供が生まれた後も、これまで通り仕事を続けられると考えるのはリスクがあります。育児や介護などで、予定通り働けなくなることもあるため、共働きを前提としたローン計画には注意が必要です。
早く返済したいので期間を短くする
早くローンを返済したい気持ちは理解できますが、返済期間を短くすると毎月の支払額が増え、家計を圧迫する可能性があります。無理のない返済期間を設定し、生活に余裕を持たせることが大切です。
固定金利より変動金利が得だと信じる
変動金利は一見、低金利でお得に見えますが、金利が上昇した場合のリスクが大きいです。将来的な金利上昇に対応できないと、返済負担が増え、家計を圧迫する可能性があります。固定金利と変動金利のリスクをしっかり理解した上で選択することが重要です。
無理な予算設定をする
住宅購入時に、無理な予算設定をしてしまうと、後々の生活が苦しくなります。自分たちのライフスタイルや将来の計画に基づいた現実的な予算設定を行い、無理なく返済できる範囲でのローンを組むことが大切です。
住宅ローンは長期間にわたる大きな責任を伴います。ここで紹介した危険な思考を避け、現実的かつ無理のない計画を立てることで、安心してマイホームを手に入れられます。
効果的なドロボウ対策


ドロボウから自宅を守るためには、効果的な防犯対策が欠かせません。犯罪者は、侵入しやすい家をターゲットにする傾向がありますが、適切な対策を講じることで、そのリスクを大幅に減らせます。



ここでは、効果的なドロボウ対策を7つ紹介します。
防犯カメラ&防犯シール(防犯意識をアピール)
防犯カメラを設置し、さらに防犯シールを目立つ場所に貼ることで、ドロボウに対して「この家は防犯意識が高い」というメッセージを発信できます。実際にカメラを設置することで、犯罪を抑止する効果が期待できます。
オープン外構にする(塀や樹木で死角を作らない)
塀や樹木で囲まれた家は死角が多くなり、ドロボウが隠れやすくなります。オープン外構にすることで、周囲からの視線を確保し、侵入者が見つかりやすい環境を作りましょう。これにより、侵入をためらわせる効果があります。
サムターンとガードプレート(外から開けられないように)
玄関ドアにサムターンとガードプレートを設置することで、外部からドアを開けられないようにできます。サムターン回し対策やガードプレートでの補強は、ドロボウが短時間で侵入することを困難にする有効な手段です。
防犯砂利&人感センサー(歩くと大きい音と光で威嚇)
防犯砂利は、歩くと大きな音が鳴るため、侵入者を驚かせる効果があります。さらに、人感センサー付きのライトを設置することで、侵入者が近づくと自動でライトが点灯し、不審者を威嚇します。これらの対策は、目立たない場所にも適用できます。
二重ロックの導入(侵入を困難にする)
玄関や勝手口に二重ロックを設置することで、侵入にかかる時間を増やし、ドロボウを諦めさせる効果があります。手間がかかりますが、その分防犯効果は非常に高く、住宅の安全性を大幅に向上させます。
玄関ドアや窓に補助錠を設置(侵入を防ぐ)
補助錠を玄関ドアや窓に追加することで、ドロボウが簡単に開けられないようにできます。特に、窓ガラスの破壊による侵入を防ぐため、防犯フィルムと組み合わせて使用するとさらに効果的です。
室内照明をタイマー設定(留守時も家にいるように見せる)
外出中でも家に人がいるように見せるために、室内照明をタイマー設定で自動的に点灯させると効果的です。これにより、留守だと思わせないことで、ドロボウに狙われにくくなります。
ドロボウ対策は、家族の安全と財産を守るために非常に重要です。ここで紹介した7つの対策を実施することで、侵入のリスクを大幅に減らせます。



自宅を安心できる場所にするために、これらの防犯対策を検討し、早めに取り入れることをお勧めします。
まとめ 情報収集して 後悔ない家づくりを
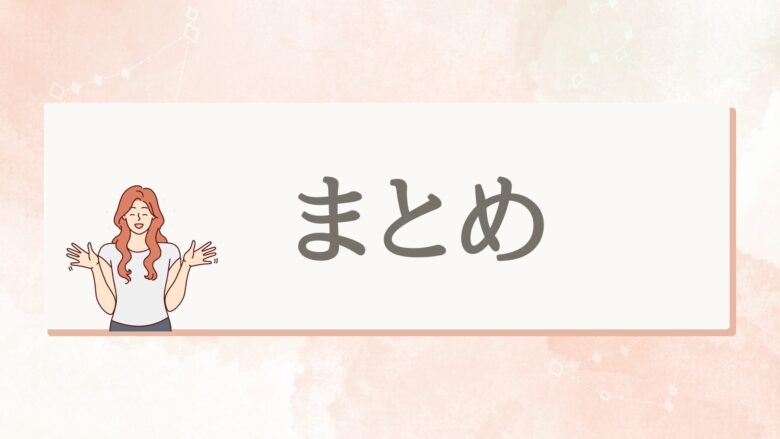
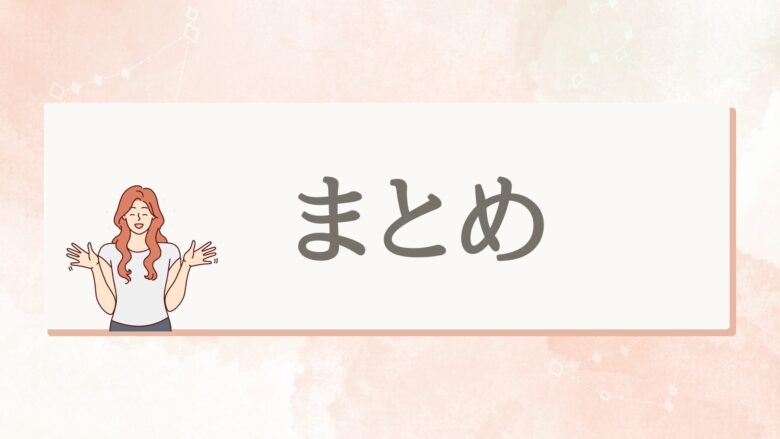
ここまでしっかりと調べているあなたは、後悔しない家づくりがができると信じています。
しっかりと情報収集をして後悔のない家づくりをしましょう!



絶対にこの努力が
後悔しない家づくりにつながります!
当サイトでおすすめする情報収集の方法は以下の2つです。自分に合った情報収集をしましょう!
簡単さ・手軽さを重視したい方はLIFULL HOME’Sでカタログ請求
情報収集には住宅カタログ一括請求がベストです。情報収集が簡単で、家でゆっくりと検討もできます。
まだいろいろなカタログを見比べていない方は絶対にするべきです。
\無料 簡単3分 ネットで完結/
» 公式 LIFULL HOME’Sで注文住宅の一括資料請求



今あなたの一歩できっと違う結果に!
やって損はないから絶対やって!
契約はリスクがあるけど情報収集はノーリスクだよ!
ぴったりな建築会社を見つけたい方はスーモカウンター
無料での圧倒的なサービス内容で、店舗数も多い!個人的には工務店が多いのもポイントが高いです!
良い点を挙げるとたくさん出てきます。
【PR】
スーモカウンターなら、カタログだけではわからない情報まで!!あなたの予算・要望にあった理想の建築会社を紹介してくれます。
\利用者満足度96.8%* 理想の建築会社が見つかる/
*スーモカウンター ご利用者アンケート/2023年5月 自社調べ



全て無料で家づくり講座も充実!家づくり初心者大歓迎!
土地探し、間取り、資金計画など全て相談したい方におすすめです。
予約を取ることでスムーズです。
他の方法も知りたい方は以下の記事も家づくりに役に立てるはずです。